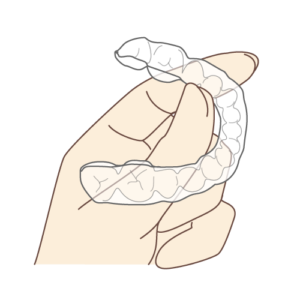マウスピース部分矯正というと、「透明な装置をつける矯正」とイメージする方が多いのではないでしょうか。
ワイヤーを使わず、見た目が目立ちにくく、自分で取り外しができることから、最近は大人の方にもとても人気のある治療法です。
では、そんなマウスピース部分矯正で、歯はどのように動いていくのでしょうか?今回は、その仕組みや、よりスムーズに歯を動かすために使われる「補助装置」についても、できるだけわかりやすくご紹介します。
⸻
■ 歯が動くのは「歯根膜」の力
マウスピース部分矯正は、ひとつのマウスピースだけで治療が完了するわけではありません。
患者さん一人ひとりの歯並びに合わせて、数十枚のマウスピースを作り、それを順番に交換しながら、少しずつ歯を理想の位置に動かしていきます。
ここでポイントとなるのが、「歯根膜(しこんまく)」という組織です。
歯根膜は、歯の根っこと、それを支える骨(歯槽骨=しそうこつ)の間にある薄い膜のような組織で、クッションのような役割を持っています。
マウスピースで歯に力がかかると、この歯根膜が片側で縮み、反対側で伸びるような状態になります。
すると、縮んだ側では骨が少しずつ吸収され、伸びた側では新しい骨が作られ、歯が少しずつ動いていくのです。これを繰り返すことで、歯並びがきれいに整っていきます。
⸻
■ マウスピースの仕組み
作られたマウスピースは、それぞれが少しずつ理想の歯並びに近づくようにデザインされています。
10日〜2週間ごとに次のマウスピースに交換し、段階的に歯を動かしていきます。
この「少しずつ動かす」という点が、体にとって無理が少なく、痛みも比較的やわらかい理由のひとつです。
ただし、マウスピースを装着している時間が短かったり、自己判断で外してしまったりすると、うまく歯が動かないこともあるため、毎日22時間以上の装着が推奨されます。
⸻
■ 補助装置を使うことで効率よく歯が動く
マウスピースだけでは難しい動きをサポートするために、「補助装置」が使われることもあります。主に次の3つです。
◎ 顎間ゴム(がっかんゴム)
上下の歯の位置関係を整えるために使う小さなゴムです。上下のマウスピースに引っ掛けて使うことで、噛み合わせのズレを改善できます。
◎ アタッチメント
歯の表面に小さな突起(レジン)をつけることで、マウスピースと歯をしっかり密着させる役割があります。これにより、歯を回転させたり、斜めに動かしたりといった複雑な動きも可能になります。
◎ アンカースクリュー
歯ぐきの骨に小さなネジ(チタン製)を埋め込んで、歯を動かすための固定源とします。奥歯を後ろに動かしたり、前歯を押し下げたりといった大きな動きに対応できます。
⸻
■ まとめ
マウスピース部分矯正は、透明で目立ちにくく、自分で取り外しもできるため、見た目やライフスタイルを重視したい方にぴったりの矯正方法です。
その仕組みは、歯の根元にある「歯根膜」の自然なはたらきを利用して、少しずつ歯を動かしていくというもの。
また、よりスムーズに歯並びを整えるためには、補助装置を併用することもあります。
専門の歯科医師と相談しながら、自分に合った治療を選ぶことが大切です。
当院では、インビザラインの認定を受けた歯科医師が、一人ひとりのお悩みに寄り添いながら治療を進めていきます。マウスピース部分矯正に興味のある方は、ぜひお気軽にご相談ください。
歯科衛生士.H